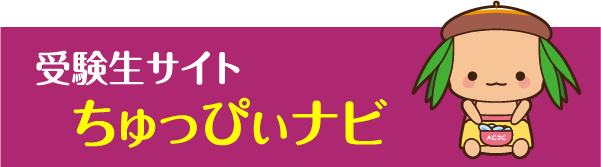検索
”PickUp"保育者の魅力についてインタビュー
「人の愛情やぬくもり」で繋がる保育士の魅力 ~青森県保育連合会会長に聞いてみた!保育士の現在~
皆さん、こんにちは。青森中央短期大学入試広報課です。
私たちは普段、高校生や保護者の方、高校の先生とお話をする機会が多くあります。キラキラ輝いた表情で夢や希望を語ってくれる方もいれば、将来に対する不安・心配事の相談を受けることもあります。
そこで今回、保育士になりたいと思っている方、またはその保護者の皆さまに対し、『保育士の現在』を知ってもらおうと思い、このページを作成しました。
青森県の保育の現場をよく知る、「一般社団法人青森県保育連合会」会長の渡邊建道(わたなべ たてみち)さんにインタビューを実施し、保育士の現状を聞いてきましたので、皆さんの進路の参考になればうれしく思います。
話し手:一般社団法人青森県保育連合会会長 渡邊 建道(わたなべ たてみち)氏
聞き手:青森中央短期大学入試広報課 野呂 竜二(のろ りゅうじ)
インタビューリスト
~多様な保育環境・働き方改革、なにより子どもたちのために~
保育士の需要はありますか?
~保育士の誤解~高水準な給与体系とスキルアップ~
保育士の給与は低いですか?
~「狭い経営観」がもたらす負の連鎖からの脱却・働く環境の改善~
給与のわりに仕事は大変ですか?
~保育士に向いている人とは~
保育士に向き・不向きはありますか?
~地元だからこそ活きる「支え人」の存在~
青森県で保育士になることの強みやメリットは?
~子どもは「人の愛情やぬくもり」なくして生きてはいけない~
保育士は、将来性のある職業ですか?
~保育は「得をする仕事」~
保育士を目指すすべての方にメッセージをお願いします。


入試:本日はお忙しい中、インタビューをお引き受けいただきありがとうございます。
まず初めにお聞きしたいのは、保育士の需要についてです。保育士という職業に需要はありますか?
渡邊氏:あります。
まず一つ目として、子どもの数は減っているものの、共働き世帯や片親世帯、気になる子どもの増加に伴う保育時間の増加など、保育需要が複雑化・多様化してきて、需要が増加しています。
二つ目は制度的な面からです。認定こども園は職員の人数に応じて、園の運営資金として支払われる施設型給付費が『加算』されるため、通常の保育所の1.3~1.4倍の職員を配置できるようになっています。
職員を多く配置することで、「保護者が安心して子どもを預けることができる園」になり、園児数の増加による収入の増加はもちろん、休暇の取りやすさ、チーム保育のしやすさなどのメリットも増えてきます。
そして何より、子どもたちにとって多くの目や手をかけてあげられるというのが、最大のメリットであり、保育士の需要が高まっている要因でしょう。
三つ目に、各園で年々「働き方改革」が進み、多くの職員を必要とするようになったことも要因に挙げられます。
さらには、退職理由の多様化もあるでしょう。新任・若手職員の早期退職により人手不足となった園は、多くがベテラン職員で構成され、さらに年を経るごとに高齢化が進んでいます。次世代へのバトンタッチがスムーズにできていないというのも大きな課題であり、これもまた保育士需要の背景に繋がっています。
残念なことに、青森県の保育施設は年に数か所ずつ減ってきています。しかし、それでもなお、「保育士の需要はある」、と言えます。

入試:保育士を目指す高校生やその保護者等から、「保育士は給料が少ないので不安」という声をよく耳にします。インターネット上の情報や近親者からのネガティブな情報を鵜呑みにしている可能性が高いと思われるのですが、実際はどうなのでしょうか。
渡邊氏:保育士の給与体系見直しに伴い全国的にベースが下げられた平成24年度と比較して、令和5年度で23%以上、令和6年度は前年度比で10%超も処遇改善される見通しです。
他職種と比較すると、例えば介護職は平成24年度と比較して20%弱、対人サービス産業では約10%の上げ幅であり、月収換算で約4万円も保育士が高くなっています。
確かに、全国の全職種平均と比べると保育士は低く見えるかもしれませんが、この中には、平均を大幅に引き上げている大企業等も含まれますので、一概に「保育士の給料は安い」とは言えません。特に青森県という地域に限っていえば、他職種と比べて高い水準にありますし、「女性」に限ればその割合はさらに高いのです。
さらに、毎年度の定期昇給に加え、勤務経験等に応じて必要な研修を受講することで、保健衛生・安全管理・保護者支援等の専門リーダーといった職務職責に対して手当がついてきますので、多くの園では、個人の努力や頑張りが給与面に反映される仕組みとなっています。
入試:定期昇給の無い中小企業もある中で、これらのようにしっかりと国を挙げての処遇改善策や手当の創設等があるのは、非常に有益な情報ですね。


入試:給与面の他に、「保育士は給料の割に仕事がきつい」という言葉もよく耳にします。このような「きつい」というイメージが定着してしまった要因はあるのでしょうか。
渡邊氏:保育業界は長い間、組織の中で専門性や効率性を発揮するための階層的で役割分業的な仕組みがありませんでした。それゆえに、園長や主任の力だけの発言や考えが強く園に反映されるため、管理者のあり方次第で組織の価値観やパフォーマンスを大きく左右する時代が平成の中頃くらいまで続いていたんです。
特に青森県の場合は、小さい規模の園で、個人商店主的な経営が多いこともあり、そこからくる「狭い経営観」が、人間関係の改善や働き方改革を妨げていた要因なのだと思います。
保育士として夢と希望にあふれていたのに、初めての就職先となった職場の環境が原因で「保育現場は大変だ」「二度と保育士はしない」という気持ちを持ってしまい、それが独り歩きして「保育士の仕事はきつい」という社会的イメージが出来上がってしまったのは、保育界としてもとても残念なことです。
しかし、平成後期からは、利用者に選ばれる以前に、保育者に選ばれる園とならなければならないという動きが出始めてきました。
「良好な人間関係を築くためには何をすべきか」、「働き方改革を推進するためにはどうすべきか」など、徐々にではありますが、園の体制や考え方も変わりつつあります。
私たち青森県保育連合会や青森県保育士・保育所支援センターでも、管理者・施設長向けに「人財確保・育成」「職場改革・離職防止」「働き方改革」「保育マネジメント」などをテーマとするセミナーを毎年開催するなどして、これらの動き等を支援する取り組みを行っています。

入試:「私は子どもが大好きで、保育士になりたいと思っていますが、正直コミュニケーションが苦手です。こんな私でも保育士になれますか。」といった不安も、よくある相談の1つです。
ズバリお聞きしますが、保育士に「向き・不向き」はありますか?
渡邊氏:極端に言えば、「向き・不向き」はあります。
向いている人は、「人が好きであること・人に関心があること」です。もっと言うなら「一人であることの限界を知り、人との出会いや関りを大切にし続けられる人」「小さな変化に感動できる人」「目先に振り回されず少し先を想いながら待てる人」が、保育者に向いている人と言えます。
反対に、「人より物が好きな人」「人との関わりが苦手な人」「計算高い人」「短気な人」「常に自分が一番な人」は、保育士に向いていないかなと思います。
しかし、「人」というものは、普段の生活はもちろん、ボランティアやアルバイト、サークル活動などで様々な人と関わり、たくさんの経験を通して、どんどん成長や変化ができる生き物です。自然や小動物と触れ合い「命」の尊さを知るのも良し、人生観が変わるほどの「一生の師や友」と呼べる良書と出会うのも良し、とにかく、将来保育者を志すのであれば、自分の目指す保育者像にどうなったらなれるのかを考え、行動する・変化することが大切だと思います。
また、新卒1年目の保育者によくある話で、「私はここで働いて、保育士に向いていないことがわかりました。」と言って保育士を辞める人がいます。
これは、「A園では向いていなかったが、実は、B園もしくはC園では、自分に合った保育ができるかもしれない。」という場合もありますから、自分の可能性を信じて、自分の将来・職業等を選択してもらいたいと思っています。
せっかく2年間苦労して得た保育士の道を、たった1つの園で働いた経験から、簡単に諦めてほしくないのです。「向いていない人」というのは、そもそも保育士の資格すら取れないのですから。

入試:「都会に出て保育士で働きたい!」という学生も少なくありません。他県での活躍も歓迎しますが、本学としては青森県への就職率も重要視しています。青森県で保育士になることの強みやメリットなどがあれば教えてください。
渡邊氏:保育士は子どもの育ちと保護者の就労を支える仕事です。誰かを支える仕事として全うするためには、その“支える人”である自分自身をしっかりと支えてくれる人が必要です。
恋人がこの「支え人」になる場合もありますが、より有効で有力な「支え人」は「家族」でしょう。シフトのサイクルに合わせてくれる、食事を用意してくれる、体調が悪い時や悩みがある時は傍らにいてくれる…。それは家族が一番です。
青森の人が都会の人になるまでは相当の時間と困難を必要とします。多くが数年で離職し、転職や青森にUターンするという人も少なくありません。
確かに都会の保育士の給料は高額で魅力的です。それならばなぜ、都会では保育士になる人が少ないのでしょうか。それは、いくら家賃補助があっても、他業種と比べて給与は低く、田舎以上に保育の仕事はきつい、と言われることが多いからです。
それでも都会で保育士になりたい方へは、地元で3年程度経験を積み、心理的にもある程度「免疫」をつけてから都会に出ることをお勧めします。


入試:2014年、オックスフォード大学の研究において、AI等の発達により10~20年後になくなる職業・なくならない職業が発表されました。保育士は代替の可能性が低い職業に分類され、保育業界でも大きな話題となりました。約10年が経過した今なお、保育士はAIに取って代わられることなく、将来性のある職業だと言えますか。
渡邊氏:はい。絶対にAI化することができない職業です。
今からおよそ800年前、ローマ皇帝フリードリヒ2世が行った実験をご存じでしょうか。彼は、教育を受けていない子どもが最初に話す言語を知るため、生後間もない赤ちゃん50人を集め、最低限の世話だけをし、スキンシップやコミュニケーションの一切を禁止するという実験を行いました。結果はどうなったと思いますか?
50人全員が1歳を迎える前に亡くなったんです。
何を言いたいかというと、子どもというのは、優しいことばや笑顔、スキンシップなど「人の愛情やぬくもり」なくして、生きていけないということです。
もちろん、保育業務の一部はAI等に代わり、保育士のサポートになり得るでしょう。しかし、無機質なAIやロボットで、「人の愛情やぬくもり」を表現することは無理ではないでしょうか。AIやロボットでは、「生命の維持」はできるかもしれませんが、「人間が育つ」という観点では、非常に疑問が残ります。

入試:「保育士になりたい!」もしくは「保育士に興味があるからもっと知りたい!」という全ての方に、メッセージをお願いできますでしょうか。
渡邊氏:私は保育者をめざす方への講話で、井桁容子先生*の「保育は得をする仕事」という言葉を引用しています。
保育者は、子ども、保護者、同僚など、いろんな人との出会いから、感動をもらったり、元気をもらったり、貴重な体験ができたりする場面が多くあります。1つ嫌なことがあっても、2つ3つ嬉しいことや楽しいことがあると、時間とともに嫌なことは和らいでいくものです。保育のまわりは、そんなプラスの出来事がたくさんあり、このような仕事はそうそうありません。
詩人の金子みすゞは「みんな違ってみんないい」と詩に綴りました。保育士もそれでいいと思います。子どもも保護者もそうですし、みんな同じはつまらないことです。AIでパターン化された模範解答が通用しない世界こそ保育の世界であり、保育の大きな魅力です。
自分が好き、だからあなたのことも大好き…そんな人が一人でも多く保育の世界に加わってくれたら嬉しく思います。
*井桁容子:東京家政大学ナースリールーム主任、東京家政大学非常勤講師を歴任。
現保育SoWラボ代表・非営利団体コドモノミカタ代表理事
- 大学案内
- 学科
- 情熱あふれるプロフェッショナル
-
教員紹介
- キーワード検索結果
- 食物栄養学科 教授:山田順子
- 食物栄養学科長・教授:清澤朋子
- 食物栄養学科 教授:田村義文
- 食物栄養学科 教授:宮田篤
- 食物栄養学科 教授:棟方秀和
- 食物栄養学科 准教授:木村亜希子
- 食物栄養学科 准教授:本間維
- 食物栄養学科 准教授:森山洋美
- 食物栄養学科 講師:池田友子
- 食物栄養学科 講師:辻村明子
- 食物栄養学科 講師:舛澤正博
- 食物栄養学科 助教:白取敏江
- 食物栄養学科 助教:外崎秀香
- 食物栄養学科 助手:森恵
- 幼児保育学科長・教授:前田美樹
- 幼児保育学科 教授:石田憲久
- 幼児保育学科 教授:鈴木寛康
- 幼児保育学科 准教授:兼平友子
- 幼児保育学科 准教授:木戸永二
- 幼児保育学科 准教授:木村貴子
- 幼児保育学科 講師:天間美由紀
- 幼児保育学科 講師:前田一明
- 幼児保育学科 助教:畑山朗詠
- 国際交流・留学
-
キャンパスライフ
-
News&Topics
- 第10回青森市環境フェア2020に参加します
- ビオトープオープンエデュケーションサイト「センス・オブ・ワンダー」開設
- CHUTAN☆ルポルタージュ 取材記事をupしました!
- 「セミの羽化鑑賞会」を開催(2020/07/24)しました
- 「翔麗祭2020」・10/3開催!
- 音楽系サークル合同イベント「虎ノ門 vol.17」(2020/12/4)開催しました
- サークルのYouTube開設しました
- スーパームーンの皆既月食がキャンパスから見えました
- FSAサークル・オンライン新入生歓迎会2021(6/17)のお知らせ
- FSAサークル新入生歓迎会を2年ぶりにオンラインで開催しました
- 動画で見る青森中央短期大学
- 2021年8月豪雨災害お見舞い申し上げます
- 「青森やさいオンラインイベント」に学生が出演しました
- キャンパスの四季 ~ 秋 ~
- キャンパスイルミネーション2021
- K-POPサークルが学内でイベントを開催しました
- 青森市環境フェア2021に参加しました
- イラストサークル制作「グリーティングカード・デザイン2022」
- Foreign Students Association主催のクリスマスパーティー2021を開催しました
- 2022年度 青森中央短期大学入学式を挙行しました
- 2021年度 青森中央短期大学 学位記・修了証書授与式を挙行しました
- 幼児保育学科と附属幼稚園との合同保育(2022/04/21)を実施しました
- キャンパスで色とりどりの花が咲いています(2022)
- 青森市広報番組「Aomo LIVE」特別番組(2022/5/24)に学生が出演しました
- 在学生レポート「カフェテリアへ行ってきました!!」
- 青森市広報番組「Aomo LIVE」(7/22)に学生と教員が出演しました
- 学生目線で青森市内の飲食店をInstagramで紹介!!
- 2022年度 青森ねぶた祭に参加しました
- 『翔麗祭2022』を開催いたします(10/8 ‣ 9)
- 第12回青森市環境フェア2022にビオトープ・プロジェクトとしてブースを出展しました
- 青森中央学院大学・青森中央短期大学カフェテリア紹介
- ビオトープサークルメンバーが園児と雪遊びをしました
- 青森市内3大学軽音楽系サークル合同イベント「MEMORIZE」に軽音楽部が出演します
- 2022年度 青森中央短期大学 学位記・修了証書授与式を挙行しました
- 2023年度 青森中央短期大学入学式を挙行しました
- キャンパスの「こぶし」の花が咲きました(2023)
- キャンパスの桜が咲きました(2023)
- 2023年度サークルガイダンスを開催しました
- 学生たちが「東北絆まつり2023青森」にハネトとしてパレードに参加しました(6/17~18)
- 青森中央短期大学・青森中央学院大学「カフェテリア・レポ」
- ビオトープサークルが附属幼稚園との合同保育を実施しました(7/6)
- 「翔麗祭2023」開催(9/16 ‣ 17)
- 中短♪音れくサークルが特別養護老人ホームで活動しました
- 幼児保育学科の学生が青森テレビ「わっち!!」に出演し翔麗祭のPRをしました
- イトーヨーカドー「青森県フェア」でお弁当をPRしました
- 「翔麗祭2023」準備中!
- 2024年度 青森中央短期大学入学式を挙行しました
- 行事予定
- 翔麗祭(学園祭)
- 学習支援センター
- 学生相談室・健康管理室
- カフェテリア
- 部活動・サークル
- リメディアル講座
- 学内ワークスタディ制度
- 学生プロジェクト支援制度
- 奨学金・教育ローン
- 後援会
- 学生会館(学生寮)について
-
News&Topics
-
入試情報
- 進路・就職
-
地域連携・高大連携・公開講座
-
News&Topics
- 2020年度 まちなかキャンパスミニ公開講座 第2回開催しました
- 青森市産官学連携プラットフォーム事業「子どものためのPFA(心理的応急処置)基礎講座」を開催しました
- 「プログラミングで造形表現してみよう」を開催しました
- 「ホタテ博士になろう~ホタテ丸ごと探検~」を開催しました
- 大豆を育てて味噌を作ろう!
- 2021年度 教員免許状更新講習について
- 青森県食育啓発冊子「AOMORIおとなのおうちごはんBOOK」に食物栄養学科の学生が協力しました
- 高校生スキルアッププログラム
- 「災害・防災をもういちど自分事として考える:東日本大震災から10年、わたしたちにできること」を開催しました
- 「和菓子づくり教室」を開催いたしました(2021/07/24)
- 「サスティナブルな地球環境~食用コオロギの可能性~」を開催いたしました(2021/07/18)
- まちなかキャンパス公開講座 「座ったままでできる日用品を使った健康ストレッチ」(2021/07/14)を開催しました
- 「セミの羽化鑑賞会」を開催(2021/07/22)しました
- まちなかキャンパス公開講座 「青森の食文化・郷土料理について学ぶ」(2021/08/11)を開催しました
- 「究極の地産地消~全国からお客を呼ぶには~」を開催しました(9/3)
- まちなかキャンパス公開講座「なぜ太る?太ると体はどうなるの?」(9/1)を開催しました
- ビオトープ公開講座「ビオトープで遊ぼう」を実施しました
- 大湊高校と専攻科福祉専攻との高大連携事業を実施しました
- 福祉セミナー「最新の介護機器で未来の介護を体験しよう」を開催しました
- 「第4回合同学修研究発表会」がWEBで開催されます
- 食文化の保護と次世代への継承-五感を使って学ぶ食育プログラムの実践-
- 「災害と食:日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)による被災地の栄養支援活動」を開催しました
- 青森南高校との連携事業「絵本をつくろう」が進行中です
- 2022年度あおもりフィールドスタディ支援事業「みんなの食堂『ベトナムを知ろう』」を開催しました
- 「親子でつくってみよう!身近なものでもしもの時のクッキング」(7/23)を開催しました
- 「さかな料理講座」(9/2)を開催しました
- 「高齢者施設に学ぶ災害への備え」(8/27)を開催しました
- 大湊高校の「大湊大学」(9/16)に参加しました
- 地域ねぶた「横内ねぶた・秋の陣」を運行しました
- 附属第一幼稚園にて、絵本読み聞かせ会を実施しました
- 「高校生と考える『子どもにやさしい避難所』づくり」(10/1)を開催しました
- 子どものための心理的応急処置(子どものためのPFA)紹介研修を開催しました【青森市産官学連携プラットフォーム事業】
- 子どものための心理的応急処置(子どものためのPFA)1日研修を開催しました【青森市産官学連携プラットフォーム事業】
- 「さかな丸ごと食育」養成講師研修会を開催しました(11/23)
- 「さかな料理講座」(3/13)を開催しました
- ホウキ作りを横内地区住民に学ぶ「魔女集会(上級)」(4/19)を開催しました
- みんなの食堂inよこうち「水餃子パーティ~中級編~」を開催しました(5/17)
- 青森市広報番組「Aomo LIVE」(5/11)に学生が出演しました
- 「いのちを守る防災意識~ライフスタイルに組み込む防災対策」を開催しました(6/10)
- 「学生STARTUP Seminar ~青森で挑戦したいワカモノへ~」(プレ・学生版起業塾)を開催しました
- 五所川原商業高校で高大連携講義を行いました(「ぶどう(スチューベン)の機能性」について)
- 「さかな料理講座」(7/9)を開催しました
- 連続公開講座「中学生・高校生対象 もしもの時のクッキング」開催のお知らせ(7/22)
- 【公開講座】身近なものでもしものクッキングが行われました。
- 「さかな料理講座」を開催しました(8/27)
- 福祉セミナー(おしごとゼミ)を開催しました(9/17)
- 日清医療食品株式会社北東北支店と連携協定を締結しました
- 「横内秋ねぶた」を運行しました(9/24)
- 「親子で他国の食文化を楽しむ:インドネシア料理を作ってみよう」を開催しました(7/29)
- 「他国の食文化を知ろう!―インドネシア料理」講座を開催しました(10/7)
- 小学生・中学生対象!ミライのおしごと体験イベント2023を開催しました
- 青森商業高校で高大連携講義「青森県産品・郷土料理を活用した弁当の開発に向けて」を実施しました
- 地域連携センター
- 高大連携
- 連携協定一覧
- 生涯学習
- 青森田中学園の公開講座
- 社会人の学び
- 大学間連携
- サテライトキャンパスFRIENDLYWINDOW
-
News&Topics
- CHUTAN食育ひろば
- 研究・出版活動
- リンク
- 50周年ページ
- 来訪者別メニュー
- 学内専用ページ
- サイトマップ
- お問い合わせ